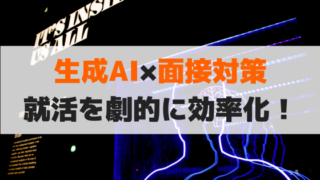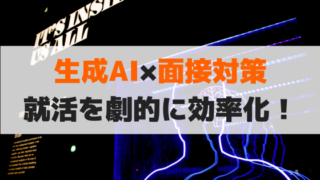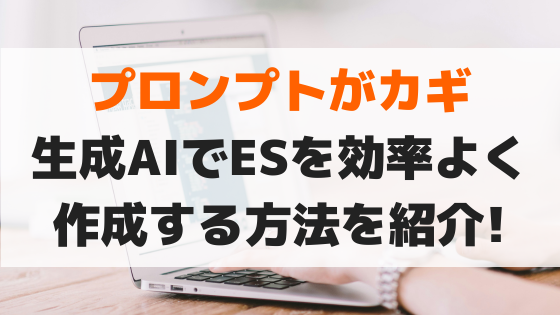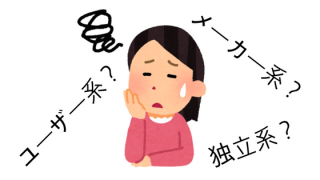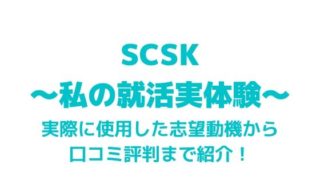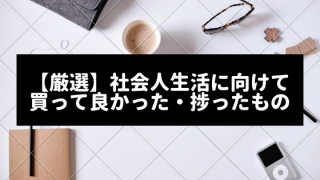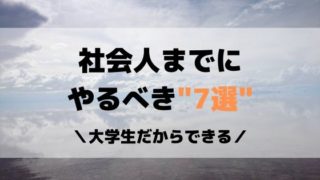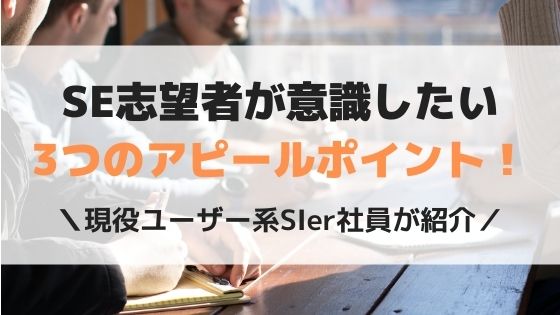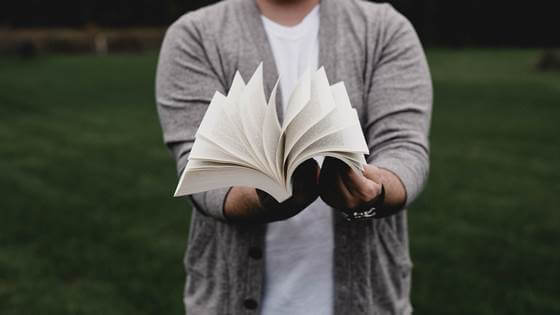就職活動においてエントリーシート(ES)の作成は多くの学生が頭を悩ませる大きな課題です。自分の強みや経験をどのように表現すればよいのか、企業ごとにどのようにアピールポイントを変えるべきか、迷うことも多いでしょう。
そんな悩みを解決する手段として、近年急速に普及しているのが『生成AI』を活用したES作成です。
生成AIをうまく使えば、短時間で質の高い文章案を作りつつ、自分らしさを保ったESに仕上げることができます。
本記事では生成AIの基礎から、実際の使い方、効果的なプロンプト作成のコツ、そして具体的な活用例まで、実践的なノウハウをわかりやすく解説します。就活を効率的に進めるヒントが見つかるはずです。生成AIを味方につけて、ES作成の時間を短縮しつつ、選考で戦える内容に整えていきましょう。
Contents
生成AIでESを書く前に知っておきたいこと
生成AIとは何か
生成AIは大量のテキストデータを学習し、人間が書いたような自然な文章を自動で作るAIのことです。近年、AI技術の進化は目覚ましく、私たちの生活や仕事のあらゆる場面に大きな変化をもたらしています。
ChatGPTやClaude、Gemini、Copilotなどが代表的なサービスとして知られています。
その生成AIは就活にも使用することができます。むしろ使用しないと、使用している就活生と差が開く一方です。生成AIを制す者が、就活を制すと言っても過言ではありません。
生成AIは与えられた指示文(プロンプト)に応じて、自己PRや志望動機、ガクチカなどの文章を一瞬で提案してくれますので、うまく使えばES作成の『下書き担当』として非常に心強いパートナーになります。
ES作成に生成AIを使うメリット・デメリット
ES作成では自己PRや学生時代頑張ったことなど、
- 何を書けばいいか分からない
- 表現がワンパターンになってしまう
といった悩みを解決するツールとして注目されています。生成AIを活用することで得られる主なメリットは以下の通りです。
- アイデアの拡張:自分では思いつかない切り口や表現を提案してくれる
- 効率化:短時間で複数パターンのESが作成できる
- ブラッシュアップ:文章の分かりやすさや説得力を高めてくれる
- 客観性:第三者目線でのチェックや改善案が得られる
生成AIの最大の特徴は与えられた情報や指示(プロンプト)に応じて、目的に沿った文章を瞬時に生成できることです。たとえば、
- 大学時代に頑張ったことを400字でまとめて
- リーダーシップを発揮したエピソードを自己PRとして書いて
など具体的な要望に応じて、構成や表現を工夫した文章を提案してくれます。
また、生成AIは大量のデータを学習しているため、さまざまな業界や職種に合わせた表現や最新のトレンドを反映した文章も得意としています。自分では思いつかない切り口や、より魅力的な言い回しを提案してくれることも多く、強力なパートナーとなるでしょう。
一方で、デメリットや注意点もあります。
- ありきたりで誰でも書けそうな文章になりやすい
- 自分の経験に基づかない内容が混ざることがある
- 大学や企業によっては、AIの過度な利用を問題視する場合もある
ただし、生成AIが作成した文章は一般的になりやすく、オリジナリティや自分らしさを加える仕上げは必須です。生成AIを使いこなすことで、ES作成の効率と質を同時に高めることができます。
生成AIでESを作成する簡単な5ステップ
ここからは生成AIでESを作成するときの具体的な流れを5つのステップで説明します。とりあえずAIに投げるのではなく、事前準備とプロンプト設計を行うことで、アウトプットの質が大きく変わります。
ステップ1:自己分析とエピソード整理
最初にやるべきことは、自分の経験と強みの棚卸しです。いわゆる自己分析です。まず自己分析をしないと何事も始まりません。
生成AIは魔法ではないので、与える材料が曖昧だと、出てくる文章もぼんやりしたものになりますので、自分の強みや経験、学生時代に力を入れたことなど、ESに盛り込みたい内容を整理しておきましょう。
次のような項目をメモやスプレッドシートに書き出しておくと良いです。
- 学生時代に力を入れたこと(サークル・研究・アルバイトなど)
- その中での役割(リーダー、メンバー、裏方など)
- 工夫した点、乗り越えた壁、得られた成果
- そこから学んだこと、今後に生かしたいポイント
この段階でエピソードが整理できているほど、プロンプトの質が上がり、AIから返ってくる文章も自分らしさを反映しやすくなります。
ちなみに自己分析には『ロジカル面接術』が使えます。この本では面接での質問に対するロジカルな回答方法や、自分の強みを効果的に伝える方法が詳しく解説されています。
特に面接官が求める『ストーリーテリング』の重要性や、自分の経験を活かした具体的な例を提示する方法が分かりやすく説明されています。就活生として必読の本ですので、是非一度手に取り、面接での自信を高めてみてください。
ステップ2:企業研究とキーワード抽出
次に志望企業や業界の情報を整理します。企業のホームページ、採用情報、IR資料、ニュース記事などから、求める人物像や価値観を把握しておくことで、AIへの指示も的確になります。
たとえば、SIer企業であれば次のようなキーワードが見つかれるかもしれません。
- 顧客の課題解決
- チームワーク・コミュニケーション
- 論理的思考・問題解決力
- 長期的な信頼関係
これらのキーワードを後でプロンプトの中に織り込むことで、その企業らしさを反映したES案を生成しやすくなります。
ステップ3:プロンプト(指示文)を設計する
自己分析と企業研究ができたら、いよいよプロンプトを作ります。ここを雑に済ませてしまうと、どれだけ優れた生成AIを使っても、出力は平凡なものになってしまいます。
プロンプト設計の基本は次の4要素です。
- 役割:AIにどんな立場で考えてほしいか
- 目的:最終的にどんな文章を作りたいか
- 制約条件:文字数、トーン、構成などのルール
- 素材:自分の経験や企業情報など、使ってほしい材料
この4つを整理してからAIに入力することで、狙いからブレないES案を作りやすくなります。
そもそもプロンプト自体を生成AIに考えてもらうことも一つの手です。上記4要素を上げて『自己PRを作成するプロンプトを生成して』でも良いでしょう。むしろ、プロンプト自体を作ってもらったほうが効率よく就活を進められます。
ステップ4:文章生成とブラッシュアップ
設計したプロンプトを生成AIに入力し、まずはたたき台となる文章を作ります。1回で完璧な案を出そうとせず、まず1案目、条件を変えて2案目というように、複数パターンを生成して比較するのがおすすめです。
気に入った案が出てきたら、次のような観点でブラッシュアップしていきます。
- 事実と違う部分はないか
- 自分の性格や話し方と違和感がないか
- 面接で深掘られても自然に話せそうか
- 抽象的な表現が続いていないか
抽象的な部分が多い場合は『この部分を具体的な数字やエピソードに置き換えて』などとAIに追加指示を出すと、より説得力のある文章に近づきます。
ステップ5:最終チェックと提出前確認
最後にAIから提案された文章をベースにしつつ、必ず自分の手で最終チェックを行います。チェックしたいポイントは次の通りです。
- 誤字脱字や不自然な日本語がないか
- 実際の経験と矛盾していないか
- 志望企業ごとのカラーが反映されているか
- 大学や企業のAI利用ポリシーに反していないか
この段階で不安があれば、キャリアセンターや友人、OB・OGなど人間にも見てもらうと安心です。生成AIと人間、それぞれの強みを組み合わせてESの完成度を高めましょう。
また、ステップ1からステップ5までの流れを繰り返すことで、効率的かつ自分らしいESが完成します。AIはあくまで『下書き担当』として活用し、最終的な仕上げは自分自身の手で行いましょう。
就活でES作成に強いプロンプトの作り方
生成AIを最大限に活用するにはプロンプト(生成AIへの指示文)の質が非常に重要です。
プロンプトが曖昧だと生成AIが生成する文章も一般的で薄い内容になりがちです。逆に具体的で詳細なプロンプトを作成すれば、自分の体験や考えが反映された質の高いESが作れます。
そのため、ここからは生成AIで質の高いES案を作るためのプロンプト設計にフォーカスします。
プロンプト設計の基本原則
良いプロンプトには、次の4つの要素がそろっています。
- STEP1役割例:あなたは新卒採用の面接官です。
- STEP2目的例:私の塾講師アルバイト経験を、SIer志望の自己PRにまとめてください。
- STEP3制約条件例:400字程度、ですます調、STAR法(状況・課題・行動・結果)で構成。
- STEP4素材例:担当教科、生徒数、成績向上の具体的な実績、工夫した取り組みなど。
この4要素が具体的であればあるほど、生成AIはあなたの意図に合った文章を作りやすくなります。
プロンプトは一度で完璧にする必要はありません。AIの出力を見ながら追加指示を出し、何度もブラッシュアップしていくことが大切です。複数パターンを作成し比較することで、自分に合った表現が見つかります。
プロンプト作成に慣れてきたら、複数のパターンを同時に作成して比較検討するのもおすすめです。例えば
- リーダーシップを強調
- 課題解決力を強調
- チームワークを強調
したパターンなど、同じエピソードでもアプローチを変えてみることで、自分に最も合った表現や構成を見つけることができます。
自己PR用プロンプトテンプレ
自己PRを作るときに使える汎用テンプレを1つ紹介します。自分のエピソードに合わせて【】内を埋めて使ってください。
プロンプト例:
あなたは新卒採用の面接官です。これから渡す情報をもとに、【志望業界・職種】向けの自己PR文を400字程度で作成してください。構成はSTAR法(状況・課題・行動・結果)とし、ですます調で書いてください。
【エピソード概要】
・活動内容:【例:塾講師アルバイトで中学生を担当】
・自分の役割:【例:学習計画の作成と保護者との面談】
・直面した課題:【例:成績が伸びない生徒が多かった】
・工夫した行動:【例:生徒ごとの理解度に合わせた個別カリキュラム作成】
・成果:【例:担当クラスの平均点を10点以上向上】
・学んだこと:【例:相手目線で課題を捉え、仮説検証を続ける姿勢】この情報をもとに、私の強みが伝わる自己PR文を作成してください。
このように、素材を整理してからAIに渡すことで、短時間で『自分らしさのある』案を生成しやすくなります。
志望動機・ガクチカ用プロンプトテンプレ
志望動機やガクチカの場合も基本の考え方は同じです。次のようなテンプレをベースに、自分の情報を当てはめてみてください。
プロンプト例(志望動機):
あなたは【企業名】の新卒採用担当者です。これから渡す情報をもとに、【職種名】志望の志望動機を400字程度で作成してください。トーンは素直で前向きな学生らしい文体にしてください。
【企業理解】
・企業の特徴:【例:SIerとして金融・通信など社会インフラのシステムを支えている】
・魅力に感じている点:【例:長期的な顧客支援とチームでの開発スタイル】【自分の経験】
・関連する経験:【例:研究・アルバイト・プロジェクトなど】
・その経験を通じて身につけた力:【例:論理的思考、課題発見力、チームでの協働】これらを踏まえ、なぜこの企業・この職種を志望するのかが伝わる志望動機を作成してください。
このようなテンプレを自分の言葉で少しずつカスタマイズしていくと、使うほどプロンプトの質が上がっていきます。
実例|SIer志望×塾講師経験のESを作る流れ
今回はSIer志望の就活生が塾講師のアルバイト経験を活かしたES作成の流れを、生成AIの活用例としてご紹介します。
元エピソードの整理
まずは塾講師の経験を次のように整理します。ここは自己分析で頑張ってください。ネタを集めないと始まりません。
- 中学生を中心に10名ほどを担当
- 模試の成績が伸びない生徒が多く、やる気も下がっていた
- 生徒ごとに弱点を分析し、個別カリキュラムを作成
- 週1回の面談で学習計画を見直し、保護者とも進捗を共有
- 結果として、担当クラス全体の平均点が大きく向上し、志望校合格者も増えた
このように【状況】【課題】【行動】【結果】をあらかじめ言語化しておきます。
SIerは顧客の課題解決力やコミュニケーション力、チームワーク、論理的思考力などが重視されるため、これらの要素が伝わるようなエピソードを選ぶことがポイントです。
プロンプト例と生成文のイメージ
上記の整理をもとに、先ほどのテンプレを使ってプロンプトを作ります。
- 役割:新卒採用の面接官
- 目的:SIer志望の自己PR(400字程度)
- 制約:STAR法で構成、ですます調
- 素材:塾講師アルバイトでの課題・行動・成果
このプロンプトを生成AIに入力すると、【課題を特定し、チームや関係者と協力して解決していく力】を軸にした自己PR案が出てきます。
そのまま使うのではなく、次のような点を自分で修正すると、より自分の言葉に近づきます。
- 自分が本当に言いたい強みの表現に言い換える
- 実際にやっていない行動が紛れ込んでいないかを確認する
- 面接で話しやすい順序に入れ替える
実際に生成AIにプロンプトを与えてみた
次に生成AIに与えるプロンプト(指示文)を工夫します。たとえば、以下のようなプロンプトをAIに入力します。
SIer志望の学生が塾講師のアルバイト経験を自己PRとして400字でまとめたい。生徒の成績向上のために工夫したことや、チームでの情報共有、保護者とのコミュニケーションなど、SIerが求める課題解決力やチームワークを意識して、STAR法(状況・課題・行動・結果)に沿って構成してください。
このプロンプトをもとに、生成AIが以下のような文章を作成します。
私は大学時代、塾講師のアルバイトを通じて課題解決力とチームワークを磨きました。担当した中学生の生徒の成績が伸び悩んでいたため、まず個々の苦手分野を分析し、オリジナルのカリキュラムを作成しました。また、同じ学年を担当する講師同士で定期的に情報共有ミーティングを実施し、生徒ごとの指導法や進捗状況を共有しました。さらに、保護者とも積極的にコミュニケーションを取り、家庭学習のアドバイスや進路相談にも対応しました。その結果、生徒全員が目標としていた志望校に合格し、保護者からも高い評価をいただきました。この経験から、顧客の課題を丁寧にヒアリングし、チームで最適な解決策を提案するSIerの仕事に強い魅力を感じています。
このように生成AIが生成した文章をベースに、さらに自分の実体験や成果、工夫した点を具体的に肉付けしていくと、より説得力のあるESに仕上がります。
また、同じエピソードでも、志望企業や職種ごとに強調するポイントを変えることで、よりマッチした自己PRを作ることができます。
- エピソードの選定(課題解決力・チームワーク・コミュニケーション力など)
- 企業や業界の求める要素を意識したプロンプト作成
- AIによる文章生成と人間によるブラッシュアップ
この流れを繰り返すことで、効率的かつ自分らしいESを作成することができます。生成AIは就活生の経験を最大限に引き出し、就職活動の強い味方となるでしょう。
ちなみにキミスカの適性検査を受けることで、自己分析に活かすことができますので、ぜひ活用してみてください。生成AIのみならず、このような完全無料の就活サービスを駆使してください。
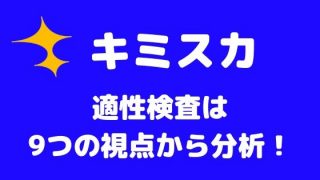
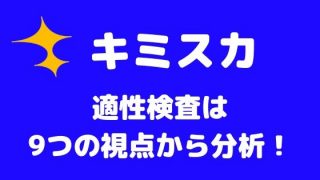
▼9項目の面から適性検査が受けられ、自己分析に活かせる▼
\もちろん完全無料で利用できます/
【まとめ】生成AIを賢く使ってES作成を効率化しよう
生成AIはES作成において非常に強力なツールです。アイデア出しや文章のブラッシュアップ、複数パターンの作成など、さまざまな場面で活用できます。しかし、AIに全てを任せるのではなく、『自分の言葉』で自分らしさを表現することが最も大切です。
AIを使いこなすためにはまず自己分析や企業研究をしっかり行い、具体的なエピソードやアピールポイントを整理することが出発点となります。そのうえで効果的なプロンプトを作成し、AIから得られた文章を自分の言葉でブラッシュアップしていくことが重要です。生成AIが苦手とする熱意やオリジナリティを加えることで、他の応募者と差別化されたESを作成することができます。
最後に、生成AIを活用したES作成で意識したいポイントをまとめます。
- AIは「下書き担当」として活用し、最終仕上げは自分自身で行う
- 事実確認やオリジナリティの追加を忘れない
- 企業ごとにカスタマイズし、第三者のチェックも活用する
- AIと人間の強みを組み合わせて、効率的かつ魅力的なESを作成する
生成AIを賢く使いこなすことで、ES作成の効率化と質の向上を同時に実現し、あなた自身の魅力を最大限にアピールできるはずです。AIと人間、それぞれの強みを活かした『ハイブリッド型』のES作成術を、ぜひ今日から実践してみてください。
ES作成のあとは面接対策に取り掛かりましょう。面接対策にも生成AIが使えますので、ぜひ活用してみてください。