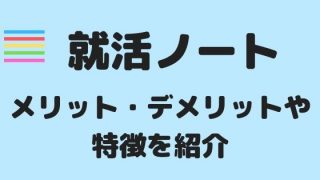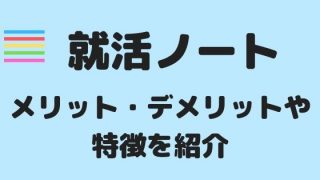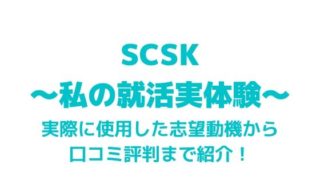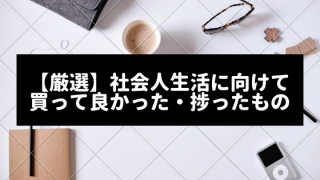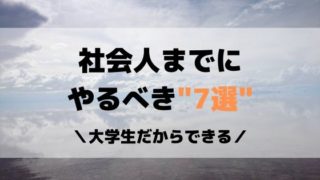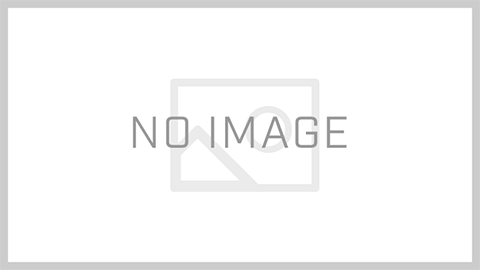多くの学生が就活を意識するのは、大学3年生の夏から冬頃でしょうか。ここ最近はもう少し早い段階かもしれません。大学主催のセミナーでも就活講座は大学3年生の内から始まります。
でも、
と、多くの就活生が思っています。私自身も就活初期は何をすれば良いのかまったく分からず、無駄な労力を掛けていました。
特に大学3年生の夏から秋にかけて、部活やサークルなどは集大成を控えています。さらに勉強や研究、アルバイトなどもあり、なかなか就活自体に時間を掛ける余裕も無いですよね。
そんな中、就活初期に意識をするインターンシップについて、
- 大学3年生の夏から就活を意識した方が良いのか
- サマーインターンシップって参加した方が良いのか
は、誰にでもある疑問です。昨今の状況を踏まえて、納得の行く就活を送りたいのであれば、必ずサマーインターンシップに参加するべきです。
理系の学生であれば研究室やゼミの課題がでも出ているかもしれません。学業も大事ですが、今後の人生に関わる就活ももっと大事です。そのため、これから理系学生でもサマーインターンシップに参加するべき理由を解説していきます。
▼就活を始めるなら『就活ノート』がおすすめ▼
\同じ就活生が作っていて、もちろん完全無料/
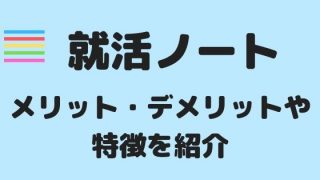
Contents
そもそもインターンシップって何?就活とどんな関係がある?
こちらの記事にも書いてあるので、多くは割愛しますが、『学生が就職前に職業の経験をするために会社で働くこと』です。
しかし、最近の就活ではインターンシップの概念が崩れ始めており、どちらかと言うと『企業の説明や紹介の場』の意味合いが強くなっています。
そのため本来であれば、3ヶ月や6ヶ月と長期が前提のインターンシップですが、最近ではいわゆる1日で完結する1dayインターンシップや、1週間程度の5daysインターンシップなどがメインです。その他にも様々なインターンシップがあり、
- 短期インターンシップ
- 長期インターンシップ
- 1dayインターンシップ
- 5daysインターンシップ
- サマーインターンシップ
- ウィンターインターンシップ
- 報酬型インターンシップ
- 実践型インターンシップ
- 有給インターンシップ
などが存在しています。この中でもサマーインターンシップと呼ばれるのは、学生が夏季休暇の7~9月頃に行われるインターンシップを一般的に指しています。授業や講義もないので、学生にとっても参加しやすいです。
この中でも私は、
- 1dayインターンシップ
- 5daysインターンシップ
- サマーインターンシップ
- ウィンターインターンシップ
のようなインターンシップに参加するべきと考えています。短ければ1日のみ、長くても1週間以内で行われる短期型のインターンシップです。これ以外は就活目的であれば、参加しなくても良いと思います。
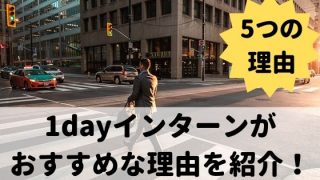
理系でも大学3年生からサマーインターンシップに参加するメリットは何?
業界研究・職種研究ができる
まず就活を始めた初期には、下記のような疑問を持った方もいるのではないでしょうか。
- どんな業界があるのだろうか
- どんな職種があるのだろうか
- どんな仕事があるのだろうか
- どんな会社があるのだろうか
- 自分には何が向いているだろうか
私は就活を初めた当初、ざっくりと『ITに関わりたい』と思っていました。もちろん、
- システムエンジニア(SE)とプログラマー(PG)の違い
- SIerとSEの違い
- IT業界とSIerの違い
- SEに求められる資質
など、全く知りませんでした。世間一般の『SE=パソコンカタカタしている人』のイメージと、私の頭の中は同様です。

そこで様々な企業のインターンシップに参加し、SIerの理解を深めていきました。例えばSIerの中にも、ユーザー系SIer、メーカー系SIer、独立系SIerなどの存在があることを知りました。
そんなのも知らないので、独立系SIerばかりに参加してしまったのは少しの後悔と、今では良い思い出です。
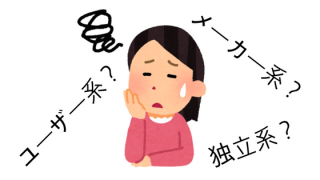
これはSIerに限った話ではありません。
- なんとなく電機メーカーに行きたい
- なんとなく製薬会社に行きたい
- なんとなくシステムエンジニアになりたい
などと思っているかもしれませんが、就活を始めると世の中には様々な業界、職種で溢れていることが分かります。しかもその業界、職種にも奥が深く、さらに詳細化をすることができます。
就活前までは知らなかった業界、職種が発見できますので、まずは広く浅くを心がけ、様々な情報収集することをおすすめします。そのためには短期インターンシップがうってつけな訳です。
企業が一番力を入れている
学生の休みと言えば、7~9月頃の夏休みや2~4月頃の春休みが一番に思い浮かべます。一般的な土日祝日よりも、そのようなまとまった長期休暇の方が時間が取りやすいです。
そのため、企業としても5daysインターンシップや1weekインターンシップなど長期のインターンシップを開催しようと力を入れています。
じゃあなぜ春休みに行うようなウィンターインターンシップよりも、夏頃に行うサマーインターンシップの方に力を入れているのか。
- 就活生の質が良い
- 本選考まで時間があり、接触する機会が多い
まずは就活生の質が段違いに良いです。一般的に、就活は大学3年生の3月解禁と呼ばれています。その中で、大学3年生の8月から就活に動いているような学生は、意識も高く、優秀である確率が高いです。
もう一つは本選考まで時間があり、接触する機会が多いからです。例えば家を買う時、あなたなら何度も現地に赴き、何度も長考するでしょう。まさかとは思いますが、たった1,2回程度で即決する事はないでしょう。
同じ考えで、企業の本音としては、長い間じっくり掛けて就活生を見極めたいと思っています。もし新卒から定年まで働くとなると、その人に掛けるコストは福利厚生や保険料を含めると平均的に3~5億円程度掛かります。
そんな大金が掛かる人材を1,2回程度の本選考の面接で判断するのはリスクが大きいです。そのため、サマーインターンシップから長期に渡り、就活生と接触する機会を増やしたい、囲い込みたいのが企業の本音です。
選考対策に繋がる
1day程度であれば、選考なしで誰でも歓迎のようなインターンシップが多いですが、2days以上となると、選考を課している企業も多くあります。
そこではES、面接、グループディスカッションと実際の本選考と同様のことが求められます。実際に私が参加した企業で、5日間と一番期間の長かったインターンシップのNECでは、ESとグループディスカッションの選考を受けました。
ESやグループディスカッションがあるということは、選考でで落ちることもあり得るわけです。選考に落ちて、インターンシップに参加できないことは残念ですが、ポジティブに考えると本選考でなくて良かったことです。
- ESで落ちた → 自己分析から再度取り組む
- テストセンターで落ちた → 勉強不足
- GDで落ちた → GDの対策
- 面接で落ちた → 自己分析、業界・企業分析、面接対策を行う
ちなみに私は面接で落ちたのですが、東京海上日動火災保険のインターンシップの面接は凄くためになりました。集団面接ですが、面接官になぜなぜ分析させられて、自分の自己分析の甘さに気が付かされました。
就活仲間が増えて情報共有ができる
インターンシップの目的としてはこれが一番大きなウェイトを占めています。意識の高い学生と知り合えるのもメリットです。私の学科だけかもしれませんが、教員志望の学生も多く、周りで就活の話しをできる友人がいませんでした。
志望している業界のインターンシップに参加することで、必然的に同じ業界を目指している就活生に出会え、就活仲間が増えることによって、情報が手に入りやすくなります。
- ◯◯はセミナーや説明会に行けば、リクルーターがつく
- △△は残業時間が少ない
- □□のテストはTG-webだった、クレペリン検査があった
- ××は面接後に小論文があった
私はこれらの情報を、就活で知り合った全く知らない学生と情報交換をしていました。まったく違う業界の会社に入社しても、今でもたまに連絡を取り合います。
本当に就活は情報戦です。情報が就活を制すと言っても過言ではありません。そのようなことからTwitterで就活用アカウントを作成するのも一つの手です。私も当時は就活用アカウントを作成し、様々な情報を得ていました。例えば
- 説明会に参加するだけでクオカード5,000円分が貰える
- ESを提出するだけで粗品が貰える
など、お得な情報も共有していました。
ちなみにリクラブと呼ばれているのも、このインターンシップから発展することがほとんどです。私が就活していた時にも何十人もの就活生とLINEを交換しましたが、インターンシップでしか連絡先を交換していません。
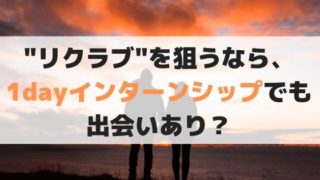
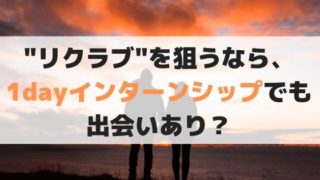
就活の本選考が有利になる可能性がある
実際に私の会社でも、サマーインターンシップやウィンターインターンシップに参加した学生には、個別で声を掛けていると新卒採用担当の方が言っていました。
このインターンシップは学生にとっても就業体験をできる良い機会ですが、企業にとっても学生に接触できる良い機会です。
至極当然のことです。企業もボランティアでインターンシップを実施しているわけではありません。当たり前ですが、数多くの就活生はその後に人事から『限定セミナー』などの接触があります。
ちなみにMARCH大学の友人は一緒に参加していたNECインターンシップで、その後リクルーターから接触があったと言っていました。残念ながら、私には接触がありませんでしたが、このような事例もあるので、真剣に取り組みましょう。
報奨金が貰えるかもしれない
これは一部の企業です。あまり期待しないでください。
長期インターンシップや報酬型インターンシップに参加することで、時給相当の給与や一時金が貰えるかもしれません。ワークスアプリケーションズやGREE、DeNAなどのIT系企業が多いようです。
これまでをまとめると、サマーインターンシップに参加することで以下のようなメリットがあります。
▼就活を始めるなら『就活ノート』がおすすめ▼
\同じ就活生が作っていて、もちろん完全無料/
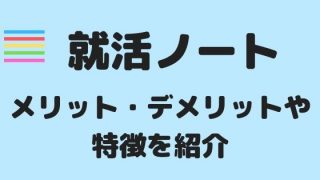
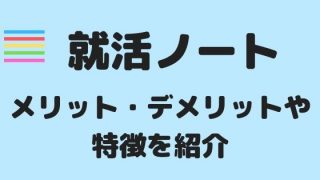
理系でインターンシップに参加するデメリットは?
遊ぶ時間や自分の時間がなくなる
どうしてもインターンシップに参加することによって、時間が取られます。大学3年生の夏というと、サークル活動では最上級生になり、遊びたい時期かもしれません。そんな中で1週間も時間が取られるのは、かなり痛いです。
卒業合宿やサークル旅行、部活動の最後の試合、友人と海や山へドライブ、彼女彼氏と夏祭りや花火大会。これらを断るにはかなりの勇気がいります。
交通費や宿泊代等のお金が掛かる
交通費や昼食代、スーツ代等がどうしても掛かってしまいます。特に地方学生が東京・大阪のインターンシップに参加、反対に東京・大阪学生が地方に参加しに行くだけで、交通費や宿泊代で◯万円以上かかります。
大学生ということもあり、お金に余裕がある学生は少ないと思いますので、その面ではデメリットです。
しかし、交通費や宿泊代が無料の企業もありますので、そのようなインターンシップが狙い目かもしれません。
また、最近ではコロナウイルスの影響により、webインターンシップの企業も増えています。自宅から参加することができますので、地方の学生でも交通費や宿泊費を気にする必要のない場合がありますので、積極的に参加できるような時代になっています。
早期選考のルートに乗ってしまう
メリットでもありデメリットです。就活、特に面接は慣れの部分があります。面接やグループディスカッション等は様々な企業の選考を通して、必ず良くなっていきます。
面接官は何を聞きたいのか、何て答えて欲しいのか。が、段々と分かるようになってきます。
そんな中、早期選考のルートに乗ってしまうと、その『面接の慣れ』がないまま本命の企業の選考が始まってしまうかもしれません。手応えを感じないまま本命企業の選考が終了してしまうと、不完全燃焼を起こすかもしれません。
実際に私も、1dayインターンシップに参加した会社の中で、早期選考のルートに乗ったことがあります。そこそこ行きたかった企業ですが、慣れていないこともあり面接がちぐはぐになって、落ちてしまった経験があります。
後々考えると、もっと遅くに受けておけば通過できたと確信していたので、悔しい一面もありました。
21卒は何が起こったか?理系でもサマーインターンシップに参加すれば有利に就活を進められた
これまでサマーインターンシップに参加した方が良いことを中心に説明してきました。
理屈は分かっているけど、本当に有利になるのかが分からないと思っている方も多いと思います。
そこで実例を出します。例えば21卒と言えば、大学3年生の1月頃からコロナウイルスが世界的に流行しました。特に2020年4月から緊急事態宣言が発令され、全国各地でも自粛ムードが広がっていきました。そのような背景もあり、4月以降は企業も採用活動を控えるような動きがありました。
そもそも大々的には3月1日に就活解禁があり、会社説明会などが始まります。そして6月1日から原則選考が始まります。
しかし、そんなの企業が守るわけがなく、実情は3月1日に解禁されたと同時に3月中旬、下旬から面接などの選考も始まっています。そのような一般的には行動が早いとされている就活生も、コロナウイルスの自粛ムードによって選考がストップしてしまいました。
それでは全員が選考ストップしていたのかと言うと、そうでもありません。
早くからインターンシップ(サマーインターンシップ等)に参加していた就活生は、実は3月前にも企業からの接触があり、内定を貰っている方もいました。そのため、インターンシップ参加組が先行逃げ切り型でかなり有利に進んでいった年でした。
今後もこのような不測な事態はあります。先に行動していた就活生だけが成功を収めるようなケースもあります。迷っている方は、とにかくサマーインターンシップにでも参加しておき、企業との接点を作っておいた方が良いです。
▼就活を始めるなら『就活ノート』がおすすめ▼
\同じ就活生が作っていて、もちろん完全無料/
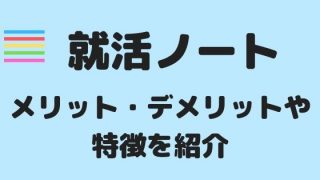
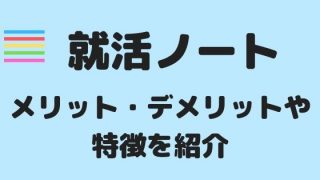
理系でもおすすめのサマーインターンシップの参加期間
先述の通り、今の日本の企業では1dayインターンシップと呼ばれる1日のコースや、5日のインターンシップ、長期のインターンシップと様々な日数があります。
あくまで、就活のためにインターンシップに参加するのであれば、5日間が一番おすすめです。
理由としては、短すぎず、長すぎないインターンシップだからです。1日だけだと、会社説明会のようなインターンシップで終わってしまい、アピールできること、人事と接触する機会が限られてしまいます。
私がインターンシップに参加したのは、下記のとおりです。
- 5日間:NEC
- 3日間:TIS
- 2日間:JR東日本情報システム(JEIS)
- 1日間:多数
この中でNECとTISはインターンシップ特別選考コースのルートに乗ることができました。具体的には、グループディスカッションの免除や早期選考開始などです。
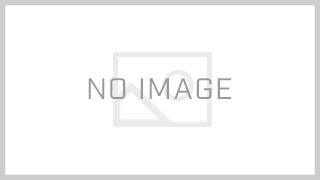
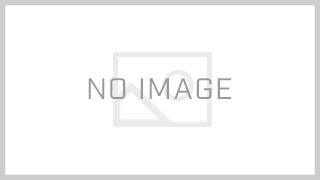
このことから、日数が長いほど選考に有利になる可能性が高いことが分かりました。
もちろん1日だけのインターンシップでも、インターンシップ特別コースというものが用意されている企業があります。
ユーザー系ならSOMPOシステムズ(旧:損保ジャパン日本興亜システムズ)、データ系ならNTTデータウェーブ、メーカー系ならばNEC通信システム、独立系ならばクロスヘッド等も早期選考や、一部選考免除がありました。


【まとめ】大学3年生から理系でもサマーインターンシップに参加しよう!
ここまで様々なメリット・デメリットを紹介してきました。何事にもデメリットが無いなんてことは有りえませんので、もちろんインターンシップにもデメリットは存在します。
しかし、インターンシップ、特にサマーインターンシップに参加することで就活を有利に進められることは明白です。就職活動のスタートダッシュを切りたいのであれば、第一に優先し、必ず参加しておくべきです。
インターンシップ情報は就活ノートに載っておりますので、是非とも登録しておきたい就活サイトです。
▼就活を始めるなら『就活ノート』がおすすめ▼
\同じ就活生が作っていて、もちろん完全無料/